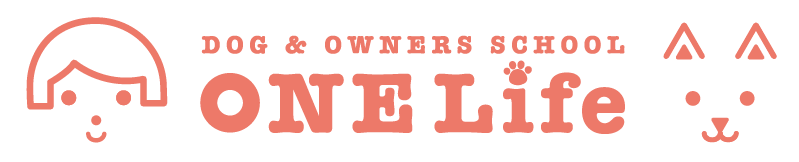噛む行動を減らすためには、噛む原因を考える必要がある
ぎふ動物行動クリニック院長・獣医行動診療科認定医の奥田です。
噛む行動に悩む飼い主さんはとても多くいらっしゃいます。噛む行動を減らしたい・なくしたいと考えていても、どう対応していいかわからないということがほとんどです。適切な対応法を選択出来れていれば噛む行動は減っているはず。それができないから、困っているんですよね。
噛む行動を減らすためにいは、噛む原因を考える必要があります。
噛む原因に対する、様々な憶測
など、様々な情報が出回っています。どれも一理ある一方、どれも完ぺきな答えではありません。
すべてが正解であり、正解でない。間違いであり、間違いではありません。
噛む行動が作られる背景には多くの要因が絡みますので、噛む行動が一つの原因で起こっていることはありません。人は、一つの単純な正解を求めがちですが、噛む原因については、一つの単純な正解はなく、複雑な複数の要因の集合によって噛む行動が作られていると理解する必要があります。
当サイトについて
当WEBサイトは、岐阜県岐阜市で行動診療を行っている、ぎふ動物行動クリニックが運営しています。当クリニックの院長奥田は、2017年に日本で8人目となる獣医行動診療科認定医を取得しています。
[blogcard url="https://amzn.to/2o35r7q"]
こちらも是非ご一読ください。
適切な治療を行えば、多くの症例で症状が緩和されます。症状が悪化する前に、行動診療を行っている獣医師にご相談にお越しください。わからないこと、不安なことがあれば、当院にお気軽にお問合せください。
(ぎふ動物行動クリニック 獣医行動診療科認定医 奥田順之)
[blogcard url="https://tomo-iki.jp/contact"]
噛む原因が分かれば、対応を設計できる
噛む原因が、複雑な複数の要因の集合であったとしても、噛む原因が分かれば、その原因をなくしていくように対応していくことができます。
つまり、噛む行動に対応していくためには、単純な一つの正解を求めるのではなく、面倒であっても、どのような要因が絡まり合って、噛む行動が発生しているのかを検討していく必要があるわけです。本稿では、この絡まり合った要因についてどのように考えていくかのフレームワークの大枠をお示しできればと考えております。それが犬に対する理解につながり、飼い主さんの悩みを解決する手助けになればと思います。
ただ、やはり一般の飼い主さんが、噛む要因を考察し、対応していくことは、なかなか難しいことです。正直、噛む行動を良く知っている専門家でなければ、その要因を整理していくことは難しいでしょう。私も、獣医行動診療科認定医を取得しておりますが、獣医行動診療科認定医をはじめとして、行動学や犬が噛む行動の対応に精通した、専門家の助言を受けることが最善の手立てであることを覚えておいてください。以下のリンクもご参照ください
[blogcard url="https://tomo-iki.jp/shiba-problem/2075"]
行動を考察するためのフレームワーク
犬が噛む理由は様々です。しかし、噛む行動を考えるときの、考え方には一定の枠組み=フレームワークがあります。フレームワークを知って、犬が噛む行動をどう捉えればいいか考えられるようになれば、犬に対する見方も変わります。
家族が犬に噛まれる時、あるいは唸られる時、飼い主家族にとっては、身体だけでなく心が痛い経験をされると思います。大切に育ててきたにも関わらず、噛まれるわけですから、なんでこんなことになったのか・・・と思って当然です。
しかし、犬にとってもそれは同じです。
「なぜ、飼い主さんは、嫌な事(=犬が噛まなければならないようなこと)をするのか・・・」
と思っているでしょう。犬と飼い主のミスコミュニケーションは、飼い主が一歩引いて、犬が噛む理由を考察することで埋めることができます。
ティンバーゲンの4つの問い
犬が噛む理由を考察する際に使える、行動学ではおなじみの概念が、ティンバーゲンの4つの問いです。
行動学者であるニコラス・ティンバーゲンは、動物の行動を理解するためには様々な次元から研究する必要性を提唱しました。
ティンバーゲンの4つの問いとは、以下の4項目から構成されます。
1.その行動は何のために起きるのか(適応)
その行動にはどのような適応的意味があるのか?
それぞれのどが見せる振る舞いが、おのおの異なる環境の中で生存し繁殖する上で、どのように役立っているかを説明しようとする視点。2.その行動は先祖種からどのように進化してきたのか(進化)
その行動は先祖種からどう変化してきたのか?
ある動物の形質に見られる表現型は過去の様々な世代の特徴を引き継いでいるため、近縁の種間での比較などを通じてその動物における行動の特異性を浮き彫りにし、系統発生の道筋を理解しようとする視点。3.その行動はどのようなメカニズムによって起こるのか(機構)
その行動を引き起こすメカニズムとは?
分子レベル、細胞レベル、神経核レベル、神経・内分泌レベル、個体レベル、社会レベルなど、様々な研究レベルから行動を解析し、各レベル間の機能的な関連を解明しようとする視点4.その行動はその個体の中でどのように発達してきたのか(発達)
その行動は、遺伝的基盤をもとに、どう習得されたのか?
あらゆる行動は遺伝と環境の相互作用の産物であるが、相互作用のあり方は多様である。対象となる行動についてこの相互作用が起こる時期や仕組みを理解しようとする視点。森裕司/武内ゆかり/内田佳子著 動物行動学 インターズー 2012 より筆者改変
動物行動学研究に対する基本姿勢として知られる、ティンバーゲンの4つの問いは、動物行動学に限らない広範な生物学分野においても使われている考え方です。これは問題行動の発生にも当てはまる視点であり、噛む行動にも当然応用できます。
犬はなぜ噛むのかを考察する
犬がなぜ噛むのかを考えるときに、このティンバーゲンの4つの問いのフレームワークを活用することができます。2の進化については除いて考えてもいいと思いますが、1.3.4.については、それぞれの噛む行動がなぜ発生するのかに答えを出す上で、有効な考え方です。
1.犬は、何のために何を目的に噛むのか?
3.犬が噛む行動は、どのような機構(身体機能や脳機能)で発生するのか?
4.犬が噛む行動は、どのように学習(発達)してきたのか?
この3つの問いにそれぞれ答えていくことで、犬が噛む行動を複数の側面からとらえることができます。一つの側面に固執して考えてしまうと別の側面を見落としてしまいます。愛犬の行動を理解し、良い関係を作り直するうえでも、この3つの側面からとらえなおすことが必要です。
犬は、何のために何を目的に噛むのか?(原因編)
1つ目の問いは、犬は何のために噛むのか?という部分です。
愛犬の行動に目を向けた時に、何が行動の目的になっているかはわかりますか?
例えば、撫でられるのが嫌い、足を拭かれるのが嫌いな犬が、体や足を触られた時に噛む行動が出たとします。これは、触られるという刺激から逃れることを目的に噛んでいると言えるでしょう。
スリッパやティッシュなど、何かの物を守って噛む場合、物を守るという目的があります。侵入者に対して攻撃する場合、縄張りを守ろうという目的があるかもしれません。
分かりにくいのが、特段目的がなくても噛むことがあるということです。例えば、他の犬に吠えかかっている時に、リードで止めると飼い主に向かって噛みついてくるような場合、これには明確な目的はなく、転嫁性の行動として発生しています。他の犬を追い払いたいという目的はあるものの、飼い主への攻撃は、八つ当たり的なものであり、明確な目的を示すことはできません。
また、葛藤によっても攻撃行動が発生します。例えば、リビングに出ていた犬をオヤツを使ってハウスさせようとしたときに、犬の中で「ハウスには入りたくないけど、オヤツは欲しい」という両立しない欲求により、葛藤が生じ、攻撃に転じることがあります。この場合も、噛むという行動に対する明確な目的ははなく、落ち着いて葛藤を処理することができずに、攻撃に発展しているという状態になります。
犬は、何のために何を目的に噛むのか?(対応編)
犬が何のために、何を目的に噛むのかを考察することは、噛む行動を減らすために必要です。
なぜならば、噛む行動の目的を除去してあげれば、噛む行動は減らすことができるからです。
物を守るために噛む場合、物を守るという目的を生じさせないことが大切です。これは予防できますね。
身体を触られるのを避けるために噛む場合、まずは無理に触ることを止めることで目的を生じさせなくすることができます。さらに、身体を触られることが怖いこと嫌な事ではないことを教えることで、触られることを避けるという目的が生じなくなります。触られることが嫌であることを理解してあげて、配慮してあげて、徐々に馴らしてあげることができれば、噛む必要がなくなります。
転嫁性、葛藤性などの場合であっても、転嫁する前の目的を除去する、先の例では他の犬に出会わないようにするとで攻撃する前の目的をなくすことができます。葛藤性の場合も葛藤を生じさせないようにする、葛藤する状況を作らないようにするということが対応になります。
犬が噛むという行動をとる場合、そこに何らかの必要性があります。噛むことで、何かを得よう、あるいは、何かを避けようとしていると考えられます。何を目的に噛んでいるのかを検討することは、犬の噛む必要性をなくしていく対応を検討することに繋がります。
犬が噛む行動は、どのような機構(身体機能や脳機能)で発生するのか?(原因編)
次に、犬が噛む行動が、どのような機構、つまり身体的な機能や、脳機能を元に発生しているかということを考えていく必要があります。
行動の中枢は脳です。脳の状態によって攻撃行動が発生しやすくなります。身体機能も脳機能と連動していますので当然影響を受けます。
身体機能に関連した噛みつきという面では、第一に身体の病気や痛みを考えるべきです。内分泌の病気や、神経の病気がある場合、攻撃行動が発生しやすくなることがあります。わかりやすいのは痛みですね。痛みがあると触られることへの不快感が増します。それによって、やめてほしくて噛むようになります。身体機能が正常であれば、噛む目的はなくなるのですが、身体機能が異常であれば、噛む目的が生じてしまいます。
脳機能に関しても同様に、異常があれば噛む行動が発生しやすくなることがあります。持続的なストレス状態に置かれた動物では、セロトニンをはじめとした脳内神経伝達物質の不均衡が生じることが知られています。セロトニンは脳のブレーキとも呼ばれる神経伝達物質で枯渇すると攻撃行動を生じ薬すなります。また、持続的なストレス状態は、人間と同様に動物でも、自律神経を失調させます。自律神経の失調状態では、交感神経が高ぶりやすくなり、攻撃行動につながることが考えられます。
このように、身体機能や脳機能に異常を来した状態では、噛む行動は発生しやすくなります。
もちろん、身噛む行動そのものは正常な行動であり、体機能や脳機能が正常な状態でも噛む行動は発生します。どのような機構で発生するのかを検討する段階で、身体や脳に異常となる機構が存在するかどうかを検討して確かめるということが重要ということです。検討して、異常なしということであれば、機構については問題がないと考えます。
例えば、飼い主に噛む犬の場合に、普通に撫でているときは噛まないけど、5分も10分も執拗に撫でると噛むという状況や、他人に噛むという場合に、見知らぬ怪しげな他人が急に触った時に噛むという状況で発生する攻撃行動は、正常な行動として身を守るために発生する攻撃行動です。さらにここで身体検査をして異常が見られず、発生した攻撃行動以外の行動に異常がなければ、身体機能や脳機能の異常の可能性は低いでしょう。
一方、小さな物音に常に反応して吠え、特にきっかけなく震えていることが多く、飼い主が近づくだけで脱糞脱尿し、リラックスした様子を観察することができないような犬に対し、手を出したら咬まれたという場合、こうした行動は正常の範囲を超えており、身体機能や脳機能の異常を念頭に置いて、対応したほうがいいでしょう。
他にも、普段は温厚な性格にも関わらず、時々クレートから出てこなくなって、そうした場合に手を出すと唸るという例もあります。こうした場合は、もしかしたら、お腹の調子が悪かったり気持ち悪かったりする時に、手を出されると唸るのかもしれませんね。下痢や嘔吐などの消化器症状は自律神経の支配が大きな要素となっており、ストレスから発生することもあります。脳機能に関わる精神面の異常が、身体機能に影響するということも、その逆も発生します。
犬が噛む行動は、どのような機構(身体機能や脳機能)で発生するのか?(対応編)
身体機能や脳機能に関して異常が考えられる場合、対応は、その機能を正常に戻すようにするということです。
身体機能の異常については、内分泌疾患・神経疾患・感覚器異常・痛みを伴う疾患など、様々な可能性が考えられますが、動物病院でしかるべき検査を行い対応を行っていく必要があります。身体機能の異常が噛む原因であった場合、それを治療すれば、噛む行動を減らすことができます。
脳機能の異常については、てんかんなどの神経系の疾患については脳波検査やMRI検査を行うことができますが、神経伝達物質の異常について客観的に把握する検査は、今のところありません。神経伝達物質の異常を疑う時には、行動の観察から異常を推測していくことになります。先に挙げた例のように、小さな物音に常に反応して吠え、特にきっかけなく震えていることが多く、飼い主が近づくだけで脱糞脱尿し、リラックスした様子を観察することができないといった状況は、正常な行動の範囲を逸脱し、異常な頻度・程度であると考えられます。こうした、適応的な範囲を超えた異常な行動がみられる場合には、神経伝達物質の異常を疑っていきます。
また、気分のムラが大きい場合も神経伝達物質の異常を疑います。よく飼い主さんから聞くのは「いつもは目が丸いのに、時々目が座っている日がある。その日に限って噛む」というコメントです。
神経伝達物質の異常を疑う場合、これを修正していくために、薬物療法を実施していきます。薬物療法では人間でも使われている、抗うつ薬、抗不安薬、抗てんかん薬などを用いて、気分を安定させていくことを狙います。異常行動を含む攻撃行動では、薬物療法によって、攻撃行動が減少することは多くあります。薬物療法だけでは根本的な解決にはならず、行動修正や環境修正と併用して行っていく必要がありますが、脳機能の異常をある程度抑えるという面では非常に有用な選択です。
また、薬物療法の中でも漢方薬の応用も選択肢の一つです。漢方・中医学の考え方では、そもそも身体と精神を分けて考えることはなく、常に影響しあうものであると考えます。そのため多くの漢方薬に精神に影響を与える作用があります。興奮を抑えるもの、不安を取り除くもの、パニックを抑えるもの、不眠を解消するものなど、多様な作用があります。自律神経を整えることも漢方薬の得意とするところです。
犬が噛む行動は、どのように学習(発達)してきたのか?(原因編)
飼い主を噛む、他人を噛むという行動を犬はどのように発達させていくのでしょうか?ここでは飼い主に噛むという行動を取り上げて考察していきましょう。
そもそも、飼い主を噛むという行動は、犬単独で学習しえない行動です。噛む対象である飼い主がいなければ、飼い主に噛む行動は成立しません。そして、飼い主の行動と犬の行動の相互作用によって、飼い主に噛む行動は成立します。つまり、噛む行動の学習とは、犬単独の学習として捉えるのではなく、飼い主との関係性も含む、相互学習の問題として捉える必要があるのです。
飼い主を噛む犬の多くは、1歳未満の時点で咬む行動を徐々に強化させていきます。家に迎えた時点で興奮性が高く、手に対して咬みつくことが多い犬ばかりでなく、家に迎えた時点では噛むことはほとんどなかった犬でも、対応次第で噛む行動が発達していきます。飼い主によって作られると言っても過言ではないかもしれません。
いくつかの過程を経て、噛む行動は発達していきます。一つは、ブラッシングや足ふきから発展していく場合です。多くの犬は初めからブラッシングや足ふきを好きではありません。嫌なことは避けたいという行動の目的から、逃げたり噛んだりといった行動をとります。その際に噛むと飼い主が手を引くという状況になれば、「噛めば嫌な事が終わる」と学習し、噛む行動を発達させていくことになります。
また、飼い主の関心を引く、遊び(狩猟ごっこ等)として飼い主の手を噛むことも子犬にはよくあります。子犬の咬みつきの行動の目的を理解していれば、噛む以外の方法で、その目的を満たす方法を提供すれば、噛む行動を減らすことができるのですが、それを把握せずに、ただ単に、噛む行動を抑えようとして、罰を使った場合に、逆に噛みつきを増やしてしまうことがあります。つまり、子犬は飼い主の関心を引く、遊びをすることを目的に噛んでいるにもかかわらず、飼い主が子犬をひっくり返して叱るとか、キャンと言うまでマズルを掴むとか、そういう対応を続けると、子犬は、飼い主の手が近づくと危険と判断するようになり、手が近づいてきたらそれを避けようと噛むようになるわけです。「噛めば嫌な事が終わる」という学習は同じように起こります。
もう一つよくあるパターンが、物を守る行動から発達する場合です。物を守る行動は、どの犬でも良く発生する生得的な行動ですが、子犬の場合、その程度は低く、物を守って唸る・噛むというところまではいかないことがほとんどです。しかし、繰り返しものを守る経験をさせることや、くりかえし無理やりものを奪われる経験をくりかえしていくと、「物を守っている時に飼い主が近づいてくると取られる=嫌な事が起こる」と学習し、物を持っている時の緊張感が高まり、結果として、物を持っている時に飼い主が近づくと物を守って唸るという行動が強く出るようになっていきます。さらに唸れば奪われないという経験を積むことで、「噛めば嫌な事が終わる」という学習が起こります。ここで格闘して奪えば、余計に飼い主に対して悪印象が付き、ちょっと近づいただけ、あるいは飼い主が動くだけで唸るようになっていきます。
他にも噛む行動が発達していくパターンはたくさんありますが、特に子犬の時期に起こりやすいものを挙げてみました。これらの経験をくりかえしていくうちに、飼い主との関係が悪化し、「どんな場面でも飼い主が近づいてくると嫌な事が起こるに違いない」と感じるようになれば、攻撃行動はさらに強化されます。もちろん「普段は別に嫌な事をしないけど、これこれこういう場面では飼い主は嫌な事をしてくる」と学習している犬もおり、その場合、飼い主から「普段はイイ子なのに、なぜかこういう時だけ唸るんです」というようなコメントをいただくことがあります。
個別具体的な噛む行動の前後の文脈だけでなく、もっとマクロな飼い主と犬の関係性という側面から見ると、犬が飼い主に対してどのように主張をするのか、飼い主がそれをどう受けるのか、飼い主が犬に対して、犬が飼い主に対してどうコミュニケーションをとるのかということも重要な要素になります。
例えば、小さなころからサークルに入れられると吠える犬がいて、それに対して我慢させることなくすぐに出してしまうだとか、人の食べ物を要求して吠えた時に与えてしまうだとか、テーブルの上に乗って人間の食べ物を食べることを止められないとか、噛む行動と直接関係のない相互作用も噛む行動に影響を与えています。
要求することで自分の主張が通る経験を繰り返した犬は、自分の要求を通すために様々に工夫して主張を展開します。それは吠えである場合もありますが、噛みつくという行動でも発生します。飼い主に対して、何かしら主張すれば嫌な事は避けられる、得たいものは得られるという印象を抱いていれば、噛む行動も発生しやすくなります。
そうした関係は、過度に依存的な犬と飼い主に見られることがあります。犬に対して依存している飼い主は、犬の要求を拒絶することはできず、かわいそうで我慢させることができない傾向にあります。犬と自分を重ねて見るために、犬の小さな苦痛
を見ることに耐えられず、受け入れることを選んでしまいます。それは飼い主自身に我慢力がないという状態も同時に表しています。
このような関係だと、噛む行動を発達させやすくなり、結果として噛む行動が定着していきます。
犬が噛む行動は、どのように学習(発達)してきたのか?(対応編)
飼い主との相互作用によって発達してきた噛む行動を減らしていくには、犬に直接アプローチするのではなく、飼い主側の対応を変化させていくことが必要です。
噛む行動の前後の状況の学習だけ見れば、噛む行動を減らしていくためには、以下のような対応が考えられます
・ 噛む行動のきっかけとなっている刺激を除去すること
・ 噛む行動のきっかけとなっている刺激と関連づいた情動を変化させること
・ 噛む行動を増やしている強化子(報酬)を除去すること
・ 噛む行動に対して弱化子(罰)を与えること
・ 噛む行動に至る前の時点の行動からの流れを止めること
・ 噛む行動に代わる行動を教えて増やすこと
ここでは個別の解説はおいおいさせていただくとして、概ねこのような選択肢があります。
噛む行動の前後の状況というミクロな視点ではなく、生活全般における飼い主と犬の関係性という視点から見ると、別の対応が必要になります。
飼い主に噛む行動がある犬と飼い主は、繰り返された経験により、飼い主は犬に対し、犬は飼い主に対して、不信感や恐怖心をを抱いており、互いにリラックスできない関係になっています。相手に何かされるかもしれないと思っているため、緊張感が増し、刺激に対して攻撃しやすい状況になっています。持続的な緊張感やストレスが発生する関係になっており、それが、交感神経の亢進などの噛む行動を増やす機構に影響を与えます。
逆に過度に依存的である場合でも、飼い主が犬の吠えや噛みつきに過剰に反応することで、犬も小さな要求が通らないことに対して過剰反応するようになっていく傾向があります。飼い主は、噛む行動を避けるために腫物を触るような対応になっていき、過剰反応が促進されていきます。
こうした状況を改善していくためには、犬が飼い主に対して、安心感・安定感を感じられるようなトレーニングや、飼い主も犬も我慢を覚えられるようなトレーニングをしていく必要があります。トレーニングは、飼い主が犬を扱う練習でもあります。それは飼い主の犬に対する自己効力感を高めていくことにもつながります。飼い主が犬を扱える自信を持つことによって、適切に犬に指導を行うことができるようになり、適切な行動を誘導して褒めることを繰り返すことで、犬は飼い主に対して安心感を増していくことができます。このような好循環を生んでいくことが、発達してきた噛む行動を減らし、適切なコミュニケーションを発達させていくことに繋がります。
(続く)