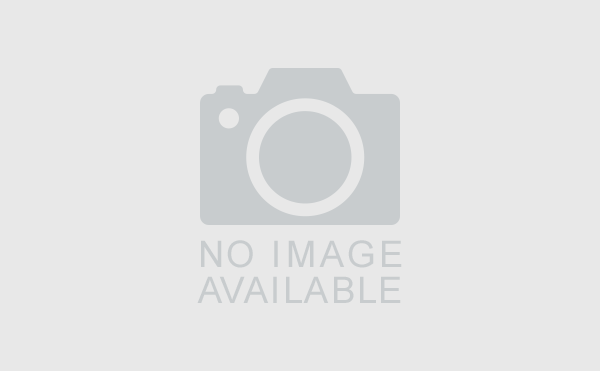本気噛みは、犬歯が刺さり出血を伴う怪我になる場合も。安全対策を最優先しましょう。生活空間を隔て、犬と一定の距離をとった生活を。身体疾患の除外、状況に応じ、薬物療法の適用も検討すべきです。生まれ持った衝動性を制御できない気質の犬がいることも確かでそうした犬には薬物療法の併用が改善のきっかけになることがあります。本記事では、今すぐ行える対処法を解説します。
本気噛みをやめさせるには
噛みつきに困られてる方に第一にお伝えしたいのが、噛まれた後に「どう叱るか」ではなく、噛みつきを、いかに「予防的に」「発生させないようにするか」ということです。本記事では、本気噛みに取り組むための5つの前提と、本気噛みに対処する具体的な8つの対処法をご紹介しています。
一人で悩まず、当院に相談してください。力になります。岐阜・浜松が遠いという方は、地域の専門家(行動診療科)をご紹介いたします。
岐阜・浜松・埼玉ともに、岐阜本院での一次受付を行っております。058-214-3442受付時間 9:00-17:00 [ 不定休 ]
お問い合わせ本気噛みは『しつけの問題』だけではない
本気噛みに悩む飼い主さんは、「私のしつけが悪かった…」と後悔されている方が多くいらっしゃします。
しかし、しつけの問題だけで、噛むようになるわけではありません。同じように育てても、同じように育つわけではありません。
遺伝の問題や、発達の問題、脳機能の問題、身体的な疾患等、飼い主さんでは対処できない問題の影響を受けて、本気噛みは発生します。
非常に敏感な脳神経を持っている犬の場合、普通にしつけを行ってもうまくいかないのは当然です。脳内神経伝達物質のセロトニンは、感情のブレーキとも呼ばれます。セロトニン代謝が生得的に弱い個体では、攻撃行動が発生しやすくなることは動物実験でも明らかになっています。特に柴犬では、セロトニン代謝を調節する薬物療法により劇的に改善する事例が少なくありません。
当院には、様々な原因で本気噛みをする犬からの相談が、年間100例以上寄せられています。犬歯が刺さり10針縫った、噛まれて指を骨折した、攻撃が強すぎて触れないどころか近寄れない、といった相談もあります。そんなレベルの攻撃はもはや飼い主さんのしつけが悪いというレベルで発生するものではありません。背景に何らかの問題が潜んでいると考えて対応すべきです。
とはいえ、何もできないかと言えばそうではありません。本記事で紹介する対応も含め、様々な対応が可能です。どうか、本気噛みに悩む飼い主さんには、ご自身を責めるのではなく、『これからできること』に目を向けていただければと思います。
当院では、しつけの範疇でのな改善法に限らず、薬物療法や、預かりを含め、様々な解決策をご提案しています。リードが外れた、捕まえられない、移動させられないという場合には、往診にて対応しています。
岐阜本院・浜松分院を中心に、愛知・三重・静岡・長野・滋賀のほか、中部圏全域から相談をいただいています。埼玉を拠点とした往診による対応も行っています。
どうぞ、一人で悩まず、私共にご相談ください。
本気噛み-動画での解説
本気噛みに取り組むための5つの前提
1.本気噛みは、「しつけ」ではなく、「治療」
犬が飼い主に噛む行動=攻撃行動は、家族や周囲への危険を伴う行動であると同時に、繰り返すことで行動が強化され定着しやすい行動です。
悪化すれば、飼い主さんや家族の身体の危険だけでなく、精神的にも追いつめてしまうことになります。また、繰り返せば、所有権放棄の原因ともなり得ます。
血が出る程の本気噛みは、しつけで直そうという考えは禁物です。特に、素人である家族だけで、ネットの情報を信じて対処すると、悪化する危険性が高いです。ネットでは一般論しか語れませんが、実際は個別個別のケースで原因が異なり、対応法も異なります。
血が出る・犬歯が刺さる・縫うような怪我になっている場合は、「治療」の領域に入っており、獣医師(行動診療科)による、診断・治療を行うべきであると心得てください。全国の獣医行動診療科は以下のリストから検索してください。
2.第一に安全確保、人の身体と心の安全を守る
初期対応では、「犬が噛まなくなること」を目指すというよりは、「犬に噛まれない生活を送ること」に焦点を置きます。家族や周囲が攻撃されない状況を作ることを最優先し、生活環境を変えるといった、犬に直接アプローチせずにできる安全確保に努める必要があります。
本気噛みの犬を治すことはプロでも難しいことです。ネットの情報を信じて「犬が噛まなくなるトレーニング」を見よう見まねで飼い主さんがすれば、流血の惨事は免れません。
当座は、「噛ませない」「噛む機会を作らない」対応に焦点を当てましょう。犬の生活空間と家族の導線に障壁(パーテーション)を設けたり、リードを装着したままにすることで着脱の必要性をなくすなど、具体的に家族が噛まれないために、今すぐできることを実施していきます。
3.攻撃行動を繰り返させないこと
安全確保が大切な理由は、これ以上攻撃行動を繰り返させ、噛みつきを定着させないためです。犬は、噛めば噛むほど、噛みやすくなります。攻撃行動を繰り返せばそれだけ定着してしまいます。
犬も噛む行動をとっているということは、それだけ追いつめられているといえます。何度も追いつめられ、噛みついている状態というのは、非常にストレスの高い状態です。噛みつきをやめさせるには、犬をストレスから解放することも必要です。
長期間、噛みつきを発生させないようにすることは、犬のストレスを和らげ、結果として攻撃が発生しにくい状況を作ることにつながります。

4.犬が本気噛みをするの原因(犬が飼い主を噛む理由)を知る
犬が本気噛みをする理由・原因は、個別個別のケースで異なります。原因がわからない状態では、「当座の対応」をとることができても、「根本的な対応」はできません。
原因を見極めるにはこちらの記事をご参照ください。
犬が飼い主を噛む12の理由|獣医行動診療科認定医が解説
【獣医師解説】犬の本気噛みは『しつけの問題』だけでなく、脳機能の異常、てんかん、神経痛やホルモン疾患で発生することも。適切な診断と治療を行うことが最善です。
本記事では、個別の対応というよりは、一般的に少なくともこれだけは行うべきという対処法について解説しています。
5.犬だけを変えるのではなく、飼い主も一緒に変わる!
攻撃行動は、犬だけでは発生しません。攻撃する対象がいて初めて攻撃行動は発生します。
そして、攻撃対象となっている人や動物との関わり合いの中で、犬が攻撃の必要性を感じ攻撃しているわけです。飼い主に対する攻撃では、飼い主の犬に対する何らかの行動や複数の行動の積み重ねが、攻撃行動を発生させる原因となっています。
そのため、犬の行動だけに注目していていては、効果的な治療を行うことはできません。飼い主の行動に目を向け、飼い主のどのような関わり合いが攻撃行動の原因を作り出しているのか推測していく必要があります。
犬だけを変えようとするのではなく、飼い主が変わることが重要です。
具体的な本気噛みへの対処方法8選
具体的な治療方法は、攻撃行動の動機づけ、発生前後の状況、攻撃対象、攻撃の頻度と程度などによってケースバイケースです。また、ここでは、当座の対処方法のみを紹介しています。
根本的な解決のためには、専門家に相談し、細かな治療計画を練らなければなりません。ここでは大まかに共通する対処方法と、少し踏み込んだ治療方法の概略について紹介します。
1.安全確保の必要性の理解
攻撃行動の治療の場面では、さらなる攻撃行動を発生させないことが何より優先されます。それは、人の安全を守るためであり、攻撃行動を定着させないためです。繰り返された攻撃行動ほど改善が難しくなります。安全確保は、人の安全のためだけでなく、学習を防ぐために第一に取り組まなければならない事項です。
安全確保のために、ハウスに入れる、リードを着けっぱなしにするといった対策が必要になることもあります。飼い主は「犬がかわいそうでできない」と感じるかもしれませんが、人が噛まれない状況を作ることが、関係を改善していくスタートラインになることを忘れてはいけません。
まずは噛まれない状態を作ることが、良い関係を作るうえでの大前提であり、優先順位が最も高い項目です。安全確保は、治療の成否を分けるポイントになるため、しっかりと対応するようにしていきます。
2.生活環境の設定
攻撃行動が発生している状況を分析し、どのような生活環境であれば攻撃が発生しにくいか検討していきます。
例えば、犬がリビングで寝そべっている時に、家族がリビングに入ってくると吠えかかり噛みつくというような状況の場合、犬がリビングで自由にしていることはリスクを高めます。サークルを準備し、ハウストレーニングを行うことで、犬がその中で落ち着いていられるようにできれば、攻撃行動の発生リスクは減ります。屋外で係留していて来客に攻撃的になる場合、係留場所を変える、あるいは、安全な室内に移すことで安全を確保できます。
このような、人と犬の生活環境・行動範囲のデザインを行うことで、噛まれる可能性はかなり下がります。

この写真は、リビングを犬に占拠されて、入れなくなってしまった家庭で、飼い主さんに整備してもらったサークルです。
しっかりとした壁が作られていますが、犬が自分自身のプライベートを守ることができるような空間を作り、自分一人で休めるようにすることは、攻撃行動の改善に大きく役立ちます。
3.きっかけとなる刺激の排除
攻撃行動のきっかけとなっている刺激を与えないようにすることで、攻撃行動の発生を減らすことができます。
例えば、ケージの前を通ると唸るという場合には、ケージの位置を変える、ケージに目隠しをする、人の動線との間に障壁を設けるなどの方法で、きっかけを与えないようにできるでしょう。リードの着脱をきっかけとして噛む場合は、リードを着けっぱなしにすることで、きっかけを排除できます。夜の時間帯にソファで寝ている犬を触ろうとすると噛むという場合には、夜の時間帯になる前に、ハウスに入れることでその状況を回避できます。
多くの場合、攻撃のきっかけになっている刺激は、犬にとって不都合な刺激です。寝ているところを起こされるといった状況の場合、わざわざ噛まれるような状況を作る必要はありません。
一方、触ることができずケアができない、動物病院に連れていくことができないといった場合には、一旦はきっかけとなる刺激を排除して攻撃行動を発生させない状況を作りますが、最終的にはケアや触られることに馴らす必要が出てきます。馴らすという作業は、高度な技術が必要ですから、行動修正の技術を持った専門家が直接トレーニングするか、指導を受けながら実施する必要があります。触ることに馴らすトレーニングは、当座の対応として行えるようなものではなく、腰を据えて、長期計画で取り組むべきものです。
4.動物福祉の状態の向上
一般に、犬の欲求が十分に満たされていない状況だと、犬は興奮しやすくなったり、刺激に対する反応が過度になったり、異常行動を示しやすくなります。食餌の内容、散歩の状況、普段の生活場所や寝床の状況、身体的異常の状況、体罰的なしつけなど恐怖や抑圧を与えるような関りがないかなど、動物福祉の状況を確認し、適切な飼育を行うべきです。
特に欲求不満は興奮度に大きく影響します。しっかりと散歩に行くことで、質の良い睡眠が得られ、自律神経の働きが適正化されます。十分な運動は、攻撃行動改善の大前提です。
5.犬のボディランゲージの理解
飼い主が犬のボディランゲージを理解できないと、犬に余計なストレスをかけ、関係を悪化させてしまいます。また、攻撃行動の前兆をとらえることができず、攻撃行動を発生させるリスクが高まります。飼い主がボディランゲージを理解できるようになれば、犬が噛むという行動をとる前に、それに気づき、回避したり原因を取り除くことができるようになります。
良く誤解されているのが、お腹を見せる行動です。犬がお腹を見せたときに「触ってほしいに違いない」と思って、お腹を撫で続けたら本気噛みされたという事例は枚挙に暇がありません。
お腹を見せる行動は、「降参のポーズ」とも言いますが、劣位行動であり、相手からプレッシャーを受けた時に表現する行動です。お腹を見せているのに触り続けるのは、降参しているのに攻め続けているようなものです。犬同士の遊びであれば、相手がお腹を見せたら、それはブレイクの合図です。飼い主さんが犬の意図を理解できるようになれば本気噛みの発生を防ぐことができるようになります。
6.飼い主との信頼関係再構築トレーニング
飼い主との信頼関係を再構築していくために、報酬を用いた、簡単なトレーニングに取り組んでいくことは重要です。一見、攻撃行動とは関係のないように思えますが、間接的に重要な影響を与えます。そもそも攻撃行動を発現している犬は、飼い主に対して不信感を抱いています。「次何してくるかわからない」、「また嫌なことをされるのではないか」と。
信頼関係再構築トレーニングは、簡単なトレーニングを行うだけですが、強要的に行うことはご法度です。トレーニングを押し付けてやらせるのではなく、飼い主と一緒にリラックスした時間を過ごすことが大切です。そして、オスワリの指示に対して、オスワリしたら報酬をもらえるといった、一定の決まった関わりを繰り替えることが重要です。
犬は、パターン化された関わりに安心感を覚えます。トレーニングはパターン化された関わりであり、犬からみて飼い主が次に何をするのか、飼い主が何を求めているのかがわかりやすくなります。それがわかることで、犬は飼い主との関係に安心感を得ることができるようになります。
7.その他の行動修正法(脱感作・拮抗条件づけ等)
飼い主とのトレーニングが進んだ上で、攻撃行動のきっかけになる刺激に対する脱感作・拮抗条件づけや、オペラント条件付けを用いた行動修正法(代替行動置換法等)を行っていきます。しかし、こうした細かい行動修正(トレーニング)のプログラムは、一般の飼い主が容易に行うことはできるものではありません。
特に本気噛みに対して、脱感作・拮抗条件づけを行うことは、容易ではありません。触ると咬む、抱っこすると咬むという犬に対して、徐々に触れるようにトレーニングしていくわけですが、失敗すればがっつり本気噛みされることになります。脱感作・拮抗条件づけでは、おやつを使いながら、触る練習をしますが、おやつで誤魔化せるレベルであればそれでいいのですが、本気噛みの場合、おやつは関係なく攻撃してくる状態も少なくありません。
決して、飼い主さん自身が、見よう見まねでやることの内容に気を付けてください。プロですら、本気噛みの脱感作は容易ではありません。預かってやらないと難しい場合も少なくありません。おやつで誤魔化せるレベルであればいいのですが、おやつが効かないレベルについては、経験豊富な専門家に相談して対応するようにしましょう。
8.薬物療法
薬物療法は、あくまでも環境修正・行動修正の補助であり、薬物療法だけで攻撃行動を制御できるわけではありません。
しかし、恐怖・不安・衝動性の高さが要因となって、攻撃行動が発生している場合は、薬物療法を実施することで、攻撃行動の発生のリスクを下げたり、行動修正が進みやすい状況にしたりすることは可能です。特に本気噛みレベル、血が出る犬歯が刺さるレベルの噛みつきは、犬の強い情動の変化を伴います。薬物療法は情動の変化をやわらげ、攻撃の程度を緩和してくれます。
薬物療法を実施された飼い主さんからは「噛まれる頻度が減った」「以前なら噛まれるところが唸る程度で済んだ」「これまでは毎回噛まれたら3回以上噛まれていたが、今回は1回だった」など、攻撃が発生しても、攻撃の程度が弱くなるという感想をよく聞きます。また、日常的な興奮の程度が下がったり、落ち着いている時間が増えたという感想もあります。
副作用としては、薬の種類によってまちまちですが、下痢、便秘、嘔吐、眠くなりやすい、逆に興奮しやすくなるなどがみられることがありますが、副作用が見られたら、投薬をやめる、薬の種類を変える、用量を減らすなどの対応をしています。一度飲み始めからずっと飲まなければならないものではなく、あくまでも効果と副作用を飼い主さんと獣医師が評価して継続するか決めるものであると考えてもらうとよいでしょう。
日本国内で主に使用されている薬物は、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(フルオキセチン)、セロトニン遮断再取り込み阻害薬(トラゾドン)、三環系抗うつ薬(クロミプラミン)、ベンゾジアゼピン系抗不安薬(ジアゼパム)です。
本質的な治療方法
犬が噛む行動が起きないようにするための根本的な治療方法は、どのような原因によって噛みつきが起こっているかによります。しかし、飼い主に噛む多くのケースでは、飼い主との関係に対して、不安や苛立ちを感じていることが多くあります。
例えば、飼い主が常に犬のことを撫でている場合、飼い主が犬に対してはっきりとした態度を示せない場合、犬は飼い主の態度に対して安心感を得ることができず、飼い主との接触の中に、苛立ちや葛藤を生むようになります。それによって、撫でられることを嫌がるようになったり、飼い主の動きに対して(次にどんな変なことが起こるかわからず)不安を感じるようになることがあります。
あるいは、自分の主張を曲げたくないという性格の犬では、自分が大切にしている資源が奪われそうな場面で攻撃的になる事があります。ソファの上に寝ている時に近くに行くと唸る・咬むといった事例はこれにあたります。ケージを守る、フードを守るという行動も同じです。
その上で、攻撃することで飼い主を思い通りに動かせたという経験をすると、自分の思い通りにしようとして攻撃するということもあります。そもそも思い通りにしようとするのは、犬自身が守りたい資源があるということ(リラックスできる寝床やフードや)もあるし、特定の家族との距離を奪われたくないという場合もあるし、逆に特定の家族が歩く事に対して不快感を感じて、それを制御しようとして攻撃するということもあります。特定の家族が立ち上がって部屋から出ていこうとすると吠える・噛むという場合、その家族に対して何らかの不快感・不安感があり、動くことを制限しようとして攻撃しているかもしれません。
いずれにしても、根本的な原因はそうした部分にあるため、犬だけを直そうとしてもうまく行きません。原因の仮説を立て、原因となっている家族側の行動をどう変化させていくか、生活環境をどう変化させていくかということが大切になってきます。
本当に攻撃行動に悩んでいる方は、できるだけ早く、獣医行動診療科をはじめとした、適切な専門家に相談してください。