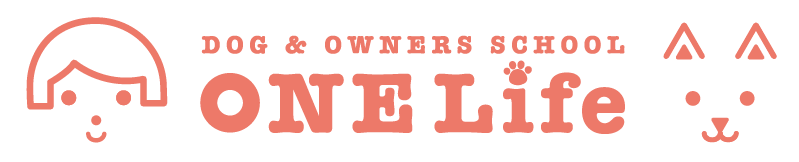ヒトでも犬でも、加齢によって認知機能は低下していきます。そのため通常の老化と病的な変化との境界線は明確に引くことは出来ません。
犬では、加齢に伴う認知機能の低下、行動の変化として、活動レベルの変化、刺激に対する反応の変化、家族や同居動物との社会的関わりの変化(喜びの表現が少なくなったり、遊びが減ったりする)、睡眠覚醒サイクルの変化、学習した行動を忘れる、恐怖や不安の反応の増大などが見られます。これらの行動変化は、脳の加齢により発生する場合だけでなく、身体疾患によって発生する場合がありますが、認知症によっても同様の変化が生じます。身体疾患による行動変化は原因がはっきりしていますが、脳の通常の加齢に伴う行動変化と、認知症に伴う行動変化を明確に区別することは出来ません。
ヒトでは、加齢に伴って大脳は委縮し、神経細胞脱落や、神経細胞同士の繋がり(シナプス)の減少が見られ、結果として、思考の緩慢化が起こります。その他、アミロイドベータと呼ばれるたんぱく質が脳に蓄積し、老人斑と呼ばれる脳内のシミができたり、タウ蛋白と呼ばれるタンパク質が細胞内で線維化し沈着した神経原繊維変化が出現します。これらの変化は、アルツハイマー型認知症の際に特徴的に見られる変化ですが、正常な加齢によっても出現します。アルツハイマー型認知症とは出現の程度が違い、一定の範囲であれば正常、一定以上の大量もしくは広範囲の出現では病的とみなされます。
認知症の犬の脳では、脳全体で顕著な萎縮が見られることが知られています。また、ヒトと同様に、βアミロイドの沈着による老人斑が認められるようになります。βアミロイドの沈着は、認知症の犬だけでなく、正常な加齢によっても形成されます。犬においては、βアミロイドの沈着の程度と認知症の症状の関連についてははっきりしたことは分かっていません。
ヒトでも犬でも、加齢により脳は衰え、変化していきます。正常の老化か、病的な変化かについては、線引きが難しいところですが、病的であるかどうかよりも、飼い主さんと犬の生活の質のレベルが保たれているかどうかが重要です。生活の質のレベルが低ければ、何らかの対処を行った方が良いに違いありません。