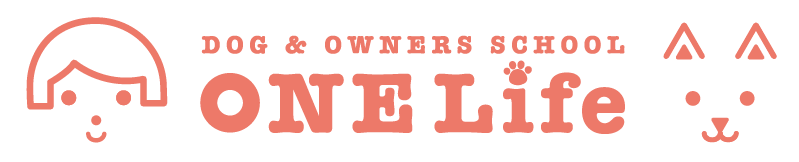犬が咬む行動は、どのような学習を経て形成されるのでしょうか。
学習の基本となる考え方は、古典的条件付けとオペラント条件付けというものがあります。
◎古典的条件付けとは
古典的条件付けとは、生得的反応(無条件反応)を引き起こす刺激(無条件刺激)と、生得的反応を引き起こさない刺激(中性刺激)を繰り返し対提示することによって、中性刺激だけで、生得的反応(条件反応)が引き起こされるようになる学習を指します。
例えば、赤ちゃんに大きな音を聞かせると鳴きますよね。この時大きな音は無条件刺激です。毎回白いネズミを見せた(中性刺激)後に、大きな音を鳴らすようにすると、白いネズミを見るだけで、赤ちゃんが鳴くようになります。この時、白いネズミは中性刺激から条件刺激に変化しています。
◎オペラント条件付けとは
一方、オペラント条件付けでは、ある状況下で、動物がある行動をとった後に、動物にとって好ましい刺激(好子)が提示されればその行動の出現頻度が増加し、逆に、動物にとって嫌な刺激が提示されるとその行動の出現頻度が減少する学習を指します。この時、行動が起こる前に動物が置かれた環境・動物に与えられた刺激のことを先行事象(弁別刺激)、発生した行動を反応、行動後に動物に与えられた刺激を、結果事象と言います。
例えば、人間の食事中(先行事象)に、飼い主さんに向かって吠える(反応)と、人間の食べているゴハンがもらえる(結果事象)ことが繰り返された場合、人間のゴハンは好子なので、吠える行動は増えていきます。
◎恐怖が関連した攻撃行動のややこしさ
さて、恐怖が関連した攻撃行動の場合、ややこしいことになると思われる方も多いと思います。
何がややこしいかというと、「恐怖条件付け」は古典的条件付けによる学習であり、咬みつくことによって嫌なことが避けられるという「攻撃行動の負の強化」はオペラント条件付けによる学習だからです。結局どっちなの?って気がします。
これを整理するためには、「動物が恐怖を感じること」と「動物が咬むという行動を実行すること」を分けて考える必要があります。
◎恐怖が関連した攻撃行動の事例
例を挙げましょう。
柴犬1歳、触ろうとすると咬むという相談。子どもの遊び相手にと、2カ月の頃にペットショップから購入。飼い始めて1ヵ月くらいは遊んで興奮している時に歯が当たることはあったが、乱暴に抱っこしたり(不安定に抱っこして抱きしめるなど)しても咬むことはなかった。4ヶ月の頃から、子どもが近づいて、手を伸ばしたり、抱っこしようと追いかけたりすると逃げ、ソファーの下に隠れたりするようになる。ソファーの下に隠れられないように、家具の位置を変えるなどの対応を行い、その後も逃げている犬を抱っこする関係が続く。5カ月の頃に、子供が抱っこしようとしたときに歯を当てる行動が始まった。その頃はまだ無理やり抱っこすることもできていたが、逃げられることもしばしばだった。6ヶ月の頃には、咬みつきが強くなってきて、血が出るほど咬まれるようになったため、子供が抱っこしようとすることはなくなった。しかし、寝ている犬に子供が近づこうとすると、歯を見せて唸るようになった。唸った時は近づかないようにしているが、9ヵ月以降は子供が1.5m位の距離に近づくと唸るようになっており、困っている。子ども意外には咬まない。子どもと仲良くしてほしいがどうしたらいいか。
◎恐怖刺激は何か?
この場合、どのような学習過程をすすんでいるのでしょうか?
この事例の様な状況では、恐怖反応を引き起こす無条件刺激は、「不安定に持ち上げられること」、「強く拘束され、圧迫されること」あたりが妥当と思います。このような刺激に対しては、恐怖反応を引き起こす動物は少なくありません。弱い刺激から馴化していく事で、恐怖反応を引き起こさなくなりますが、今回の事例では、そのような取り組みは行われなかった前提で考えます。
◎恐怖反応とは
また、この場合の恐怖反応とは何でしょうか?恐怖反応には、内面的に知覚される反応と外面的に観察できる反応があります。内面的に知覚される反応とは、人間であれば感情として本人が知覚するイメージのことを指します。しかし、動物では内面的に知覚される反応は観察できませんので、除外して考えるべきでしょう。動物における恐怖反応とは、恐怖刺激によって、交感神経が亢進し、アドレナリンなどのストレスホルモンの分泌によって起こる反応のことを指します。瞳孔が散大する、毛が逆立つ、心拍数が増加する、震えるなどの反応がこれにあたります。
1次的な恐怖刺激を受けることで、動物が逃避する行動については、学習による行動と対比して本能的な行動と言われることがありますが、哺乳類の様な高次の脳機能を持つ動物において、どこまでが本能的な行動か、どこまでが学習による行動が識別することは難しいと言われています。
◎恐怖条件付けの過程
「不安定に持ち上げられること」、「強く拘束され、圧迫されること」という恐怖刺激によって、「瞳孔が散大する、毛が逆立つ、心拍数が増加する、震える」などの反応が引き起こされている状況は、無条件刺激によって、無条件反応が引き起こされている状況です。
ココから、「子供が近づいてくる」(中性刺激)と、「不安定に持ち上げられる」、「強く拘束され、圧迫され」(無条件刺激)ることが繰り返し対提示されることで、古典的条件付けの学習が起こり「子供が近づいてくる」(条件刺激)だけで「瞳孔が散大する、毛が逆立つ、心拍数が増加する、震える」(条件反応)を引き起こすようになるという学習が成立することが、恐怖条件付けの学習と言えます。
◎オペラント条件付けの学習過程
まずは、子供が近づいてくる⇒恐怖反応と言う、古典的条件付けが成立しました。子どもが近づいてくることによって、恐怖反応引き起こされること(=嫌子)を予測している状態と言えます。
では、ここからオペラント条件付けの学習がどのように進むか考えてみましょう。
子供が近づくと(先行事象)、犬が逃げる・ソファーに隠れる(反応)ことで、子供に関連して予測された恐怖反応から逃れることができた(結果事象)
という状況が繰り返し引き起こされることになります。
結果事象として、子供に関連して予測された恐怖反応から逃れることができた(=嫌子がなくなった)ことで、負の強化の学習が働き、犬が逃げる・ソファーに隠れるという反応の発生頻度を上げることになります。
咬む・唸るという状況も同じで、咬む・唸ることによって、子供が近づいてくる(=嫌子)を避けることができるために、その行動が強化されていくことになります。
また、5~6ヶ月の部分では、弱く咬んだ時は、逃げられないけど、強く咬めば逃げられると学習することで、徐々に咬みつきが強くなり、子供が耐えられないレベルまで強くなるという学習が起こっていると言えます。
◎体罰的なしつけで失敗する場合
さらに、この事例に限らず、体罰的なしつけを中心として、飼い主さんが中途半端に犬を従わせようとすること、悪化していきます。
つまり、咬むのはダメだということで、押さえつけけたり、無理なマズルコントロールに挑戦したりすることです。こうした行為は、恐怖条件付けの学習と強めると同時に、オペラント条件付けの学習も強化します。
恐怖条件付けでは、より強い恐怖を繰り返し提示することになるので、学習が促進されることは明白です。
オペラント条件付けでは、飼い主さんが体罰的な方法を実施しても、犬はより抵抗しますので、大抵の場合、犬の強い抵抗に飼い主さんが負けて、咬まれて撃退されます(負の強化)。これを繰り返すことによって、犬は咬む力を強くしたり、暴れる力を強くするように学習していきます。
強制的なしつけで咬まなくなる場合は、人間側が完全に咬むという行動に反応せず、犬を制しきれる場合です。つまりは、消去の学習をさせるわけですが、この場合、恐怖条件付けの学習を強化してしまうことも考えられます。条件によって、実施できる場合とそうでない場合が存在するでしょう。
◎まとめ
恐怖が関連した攻撃行動においては、古典的条件付けとオペラント条件付けが両方とも関与しています。また、それぞれの状況で、何が反応を引き起こしているのか、変わってきますので、個別の事例については個々に分析を行う必要があります。
恐怖が関連した攻撃行動を改善するためには、この両者の学習がどのように関わっているかを把握し、問題となっている行動(咬む・唸る)などが発生しないようにサポートしていく必要があるでしょう。