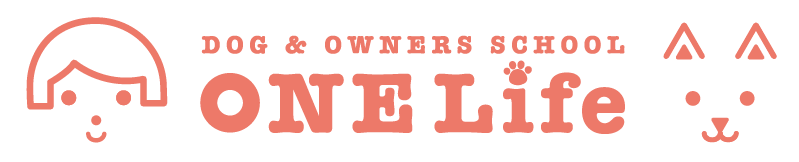攻撃行動の原因を考える際には、攻撃行動の目的、機構、発達と言う、複数の側面からの検討が必要である。
攻撃行動の目的
攻撃行動は、犬が生き延びる上で自分の身を守ったり資源を守ったりする上で必要な行動であり、異常な行動ではない。犬が進化の過程で受け継いできた正常な行動である。攻撃行動が問題になるのは、人が伴侶として暮らすことを目的として飼育している中で、人が攻撃してほしくないと思っている対象に対して攻撃する場合であり、番犬が害獣に対して攻撃することは問題にならない。問題となる場面においては、犬はその攻撃が自分にとって必要であるから攻撃している。一方、人は攻撃行動が不都合であるからやめさせたいと感じ、その対立から問題となっているのである。この構造を理解し、犬がなぜその攻撃行動を必要としているのかに目を向けることが必要である。
犬が攻撃行動を必要とする理由は様々であるが、恐怖から逃れるため、自分の身を護るため、大切な食餌を守るため、縄張りを防衛するためなどが挙げられる。これらは嫌な刺激から逃れ、自分の身をはじめとした大切な資源を守るための防衛的な攻撃である。一方で、遊び関連性攻撃行動では、飼い主の関心を引くために咬む行動が見られる。これは、犬自身の得たいものを得るための攻撃である。
飼い主の膝の上で寝ている犬を撫でると咬むというような症例は少なくないが、こうした犬では「このまま飼い主の膝の上で寝ていたいが、飼い主に触られて眠りを邪魔されるのは嫌だ」と言う葛藤状態を処理できずに攻撃していることが多い。この場合、攻撃行動そのものに強い目的があるわけではなく、衝動から攻撃してしまったというような状態である。また、同種間攻撃行動を止めようとした飼い主を咬んでしまう転嫁性攻撃行動も、飼い主を攻撃する目的は特にない。
攻撃行動の機構
行動の中枢は脳神経であり、攻撃行動も脳神経に制御されて発生している。脳神経は遺伝子、胎生期環境、母性行動、社会化期における生育環境などの影響を受けて多様な発達を遂げる。さらに若犬期以降も環境の変化に応じて、流動的に変化を続ける。脳神経細胞の配列、シナプス結合、神経伝達物質の多寡、受容体やトランスポーターの発現の状況などの脳神経の基盤が、攻撃行動を発生させやすくも発生させにくくもする。
攻撃行動の発現のしやすさは遺伝するため、犬種によっても、家系によっても、その程度は異なる。攻撃行動が発生しやすい犬種については、前述した。遺伝子が同じであっても、胎生期環境や母子行動の多寡等によって、エピジェネティックな変化が起こり、表現型は変化する。胎生期に母犬が高ストレス状態に置かれると、母体で分泌されたコルチゾールが、母胎内の子犬の発達に影響を与え、出生後の基礎的なストレス応答や不安行動が大きくなる可能性が示唆されている。また、げっ歯類での実験ではあるが、グルーミング頻度の高い母ラットに育てられた子ラットは、不安行動が小さいことが示されている。
犬では、生後4週~12週の期間が社会化期と呼ばれ、様々な社会的な刺激に対して強い警戒心を抱かずに、順応しやすい時期であると考えられている。社会化期は、ある刺激が自分にとって好い刺激か嫌な刺激か判断する役割を担う大脳辺縁系の偏桃体が未発達な時期である。社会化期に出会った刺激は、偏桃体での処理を受けずに入力され記憶されるために、犬自身にとって嫌なものであるという判断を受けにくくなるものと考えられる。
また、脳は効率的な情報処理を目指して変化する性質を持つ。脳内のシナプス結合の量は、一時期多くなるが、成長するに従って必要なシナプスを残して、不必要なシナプス、つまり使われないシナプスは脱落していく。社会化期に刺激を受け強化を受けたシナプス結合は将来的にも残り脱落しにくくなるが、社会化期までに出会ったことのない刺激に関してはその情報を処理するシナプス結合が脱落することで、恐怖や不安を感じやすくなるのかもしれない。
社会化期以降についても、脳の機能は常に変化し続ける。持続的なストレス環境に置かれた場合、コルチゾールをはじめとしたストレスホルモンが脳機能に影響を与える。コルチゾールは、脳神経細胞に作用して、Ca2+チャネルを開口する。ストレス応答の初期では、神経細胞の処理速度を高め、ストレスに対応しようとするが、長期的にストレス応答が続くと、細胞内のCa2+イオン濃度が高まり、神経細胞死を引き起こす。特に神経細胞の刈込と新生が活発な海馬において影響が顕著であり、長期的なストレス環境下に置かれた動物では、海馬の萎縮がみられることが知られている。
持続的なストレス環境は、脳内神経伝達物質の代謝にも影響を与える。人間のうつ病では、長期的なストレスが引き金となって、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンなど神経伝達物質が枯渇することでうつ症状が引き起こされるとする、モノアミン仮説が提唱されている。動物においては、セロトニンノックアウトマウスや、セロトニンの前駆物質であるトリプトファン欠乏食を与えたマウスにおいて攻撃行動の増加が確認されている。犬においても、持続的なストレス環境によって、セロトニンなどの神経伝達物質の枯渇を引き起こされ、それが攻撃行動の要因になると考えられる。
攻撃行動の発達
攻撃行動は、攻撃の対象が人であれ、犬であれ、他の動物であれ、攻撃の対象が必要であり、攻撃を行う犬単独では発生しない。また、その犬が、攻撃の特定の対象(飼い主等)や対象群(他人全般、他の犬全般等)に対して、子犬の時期から攻撃することは少なく、成犬になっていく過程で攻撃行動を発達させていくことがほとんどである。攻撃行動の発達の過程では、攻撃対象の反応によって、攻撃が強くも弱くもなる。つまり、攻撃行動の原因を考える際には、攻撃対象との相互作用によって、どのように攻撃行動が発達したかを考える必要がある。
中でも、飼い主に対する攻撃行動では、攻撃対象である飼い主との相互作用が大きく影響する。結果として攻撃行動が繰り返されている場合、攻撃対象である飼い主や、飼い主が行う何らかの行為に対して、恐怖や嫌悪といった攻撃行動を発生させるような強い情動が関連づいているか、あるいは、攻撃行動によって犬が何らかの良い結果を得ていると考えられる。多くの場合、この両方が同時に起こっていると考えられる。
例えば、飼い主から撫でられるという刺激に対して攻撃行動を示す犬の場合、飼い主から撫でられるという刺激に対して嫌悪感を抱いているかもしれない。子犬の頃は、嫌悪感が強くなかったとしても、飼い主が執拗に不快な撫で方を繰り返した場合、徐々に嫌悪感が強まっていることも考えられる。この時、犬が唸る・牙を見せる・歯を当てる・咬むといった攻撃行動を飼い主に示したとき、飼い主が手を引いて、撫でるのをやめたとすると、犬は「攻撃すれば嫌な事が終わる」と学習するだろう。結果として、撫でられるという不快な刺激から逃れるという、犬にとっての良い結果を得るために攻撃行動を行うようになる。
また、はじめは撫でられる場面だけで攻撃行動を示していたにもかかわらず、犬が寝ている時に飼い主が近づくだけで唸る、ケージのそばを通るだけで唸るといった別の場面でも攻撃行動が発生するようになることがある。こうした状況は、飼い主が撫でることによって、犬に対して不快な刺激を示し続けたことで、「撫でられることが不快」という状態から、「飼い主の接近自体が不快」という状態になり、攻撃行動発生の場面が般化した場合に起こる。このような攻撃行動の発達は、飼い主が犬の行動の目的やボディランゲージを理解できず、「撫でてあげているのに突然咬まれる」といった認識を持っている場合に発生しやすい。
飼い主に対する攻撃行動では、飼い主との相互作用によって発達してきた行動であるから、飼い主側の接し方の問題を抜きにして原因を探ることはできない。飼い主側がどのような環境を提供し、どのような接し方を行ってきたのかを把握することで、何に対して強い情動を抱き、攻撃することでどのような良い結果が得られているのかを分析することが、攻撃行動の原因を探ることになる。
オンライン行動カウンセリングのご案内
当院では、社会情勢を踏まえ、オンラインでの行動カウンセリングを実施しております。適切な治療を行えば、多くの症例で症状が緩和されます。オンライン行動カウンセリングの詳細はこちら。
症状が悪化する前に、行動診療を行っている獣医師にご相談ください。わからないこと、不安なことがあれば、当院にお気軽にお問合せください。
(ぎふ動物行動クリニック 獣医行動診療科認定医 奥田順之)
[blogcard url="https://tomo-iki.jp/contact"]